 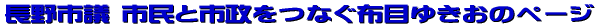 |
|
|
|
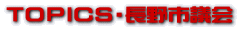
   |
 学校給食へのカビ米混入、追跡調査で「安全を確認」 学校給食へのカビ米混入、追跡調査で「安全を確認」
 学校給食における冷凍加工食品の使用割合を調査 学校給食における冷凍加工食品の使用割合を調査
|
 安全確認とはいえ、「食の安全」は万全ではない 安全確認とはいえ、「食の安全」は万全ではない
学校や保育園の給食で危ぶまれた「カビ米の混入」は、調査の結果、安全が確認されました。10月8日の会派への説明会で明らかに。とはいえ、輸入汚染米の危険と隣り合わせであることを痛感させた今回の事態。安い食材を使用せざるを得ない学校給食センターの在り方が問われます。地産地消の徹底と自校給食方式の再検討が必要だと考えます。そもそもはWTO(世界貿易機構)の交渉でミニマムアクセス米としてコメの輸入を受け入れてしまったことが問題。それで減反・減反ではコメ農家はやり切れません。国の食糧政策の抜本的な見直しが必要です。
 冷凍加工食品の使用状況を調査 冷凍加工食品の使用状況を調査
9月22日、議会最終日に「カビ米混入の恐れ」について説明を受けた際、給食の副食に冷凍加工製品が使われていることや、東京の会社である「すぐる食品㈱」が製造した問題の食品「厚焼き玉子」につなぎ用としてデンプン(このデンプンにカビ米が使われた恐れありとされたもの)が使用されていることにも驚き、学校給食における加工食品のカロリーベースでの使用状況の調査をお願いしました。
先ごろ、教育委員会から「献立における冷凍加工食品調査」の結果をいただきました。今年の6月での第一から第三・豊野の給食センター、戸隠・鬼無里・大岡の給食共同調理場での集計です。
| センター |
コース |
給食
日数 |
品目数 |
冷凍加工食品
総重量(kg) |
総カロリー量
(kcal) |
冷凍加工食品
カロリー量 |
総カロリーおける
冷凍加工食品の割合 |
| 第1給食センター |
小1 |
21 |
7 |
1463.0 |
12,914 |
560 |
4.3% |
| 第2給食センター |
小 |
21 |
6 |
1312.0 |
13,591 |
522 |
3.8% |
| 第3給食センター |
小 |
21 |
10 |
1850.2 |
14,024 |
725 |
5.2% |
| 豊野給食センター |
小 |
21 |
7 |
281.9 |
14,098 |
639 |
4.5% |
| 戸隠共同調理場 |
小 |
20 |
0 |
0.0 |
13,341 |
0 |
0.0% |
| 鬼無里共同調理場 |
小 |
21 |
2 |
12.5 |
14,419 |
90 |
0.6% |
| 大岡共同調理場 |
小 |
20 |
1 |
6.4 |
12,744 |
119 |
0.9% |
| 合計(小・中の計) |
330 |
80 |
11,898.6 |
234,489 |
6,957.5 |
3.0% |
*調査集計では、小1・小2・中に分けてあるものを小1・小のみを表記。
*合計は小・中の総計
品目(製品)では、かにだんご、エビフライ、オムレツ、ハンバーグ、ぎょうざ、ミートボール、えびしゅうまい、肉だんご、アンサンブルエッグ、ササミフライ、きんぴら包焼き、鮭入信田などが並びます。
この調査結果をどのように評価するのかは、なかなか難しいところです。カロリーベースでの冷凍加工食品の割合が平均3.0%を高いと見るか、低いと見るか、この点はご意見をいただきたいと思います。詳しい資料を必要とする方はご連絡ください。
注目すべきは、合併4町村のうち戸隠・鬼無里・大岡地区は、冷凍加工食品が全くまたはほとんど使われていない事実です。地元の食材で手作りが基本ということなのでしょう。子ども達の「食の安全」を考える重要なヒントがここにありそうです。
もう一つ注目すべきは、上記の表は月平均の数字であって、例えば、ハンバーグが副食の場合はカロリーで15.5%とか、ぎょうざの場合は26.4%とかの割合になることです。すべて加工地は日本ですが、今回のカビ米のように材料の原産国までたどることは今の法整備のもとでは困難といわなければなりません。不安を漠然と感じるのは私だけでしょうか。
 9月20日付の「徒然日記」、ニュースを聞いての所感を改めて転記します。 9月20日付の「徒然日記」、ニュースを聞いての所感を改めて転記します。
…(台風一過で催された運動会の)さわやかな気持ちを一変させたのが、学校給食へのカビ米混入の恐れのニュース。農水省の調査結果で、県内ではカビ米などの事故枚を不正転売した業者がいないとのことで一安心していた矢先、しかも学校給食の食材へのカビ米混入はショックな事件です。加えて長野市内での菓子店異臭あん、有害物質メラニン混入の恐れある中国産牛乳と、食の安全が根本的に揺らいでいます。
生産-加工-流通-消費のいずれかの段階で、悪意ある業者が存在すれば、「食の危険」は国境を越え、県境を越え、一挙に広がってしまうという現代のグローバル化する食流通の実態が浮き彫りに。この対極に「地産地消」があります。安全・安心な食材の提供を保証するには、「地産地消」の徹底しかないのではと考えます。もっとも、これも善意ある生産者を大前提としていますが…。
農水省のチェックの甘さが大問題となり、農水大臣の辞任、事務次官の更迭という事態となりました。選挙目当ての対応が見え見え。根本的な解決には程遠い政治の対応です。ところで、このチェックの甘さですが、「食糧管理法(食管法)」時代には、強制的な立ち入り調査権が付与されていたそうです。ところが、ミニマムアクセス米の輸入、米の供給・流通の自由化をうたった「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(食糧法)」のもとでは、強制権のない調査のみ。農水省・農政事務所が業者に資料開示を求めても任意提出の壁に阻まれ、真相に迫れない限界があるのだとか。長野農政事務所の職員の話です。法制度に基本的な欠陥がありそうです。「消費者基本法」とも連動できる厳しいチェック体制を再確立することが不可欠です。
|
このページのトップへ |
|
|